葬儀の現場でよく聞かれる質問のひとつに、
「ご飯と団子って、どうやって用意するんですか?」があります。
結論から言うと――浄土真宗以外の仏教葬儀では、ご飯・お団子・お茶をお供えするのが一般的です。
意味については諸説ありますが、私がいちばんよく耳にするのは「四十九日間のお弁当説」。
初七日(亡くなってから7日目)にご飯を召し上がり、その後は七日ごとにお団子をひとつずつ食べて、四十九日を迎える。
このため団子は6つ作る…という説ですね。(地域や宗派によっては13個という場合もあります)
お供えしたご飯と団子は、告別式でのお花入れの際に棺に納めます。
少し大げさな言い方ですが、私はこれを「亡くなった方のためにできる最後の手仕事」だと思っています。
しかし最近…
10年前は「自分たちで作る」のが普通でしたが、いまや葬儀社が数千円で作ってくれるケースが増えました。
依頼するのが悪いわけではありません。葬儀の準備は想像以上に忙しいですから。
それでも、できればご家族に作ってほしいのです。
丸めるとき、ふと故人の笑顔や思い出がよみがえる。
その時間は、料理以上の意味を持ちます。
作り方は?
この記事でレシピまで書くと長くなりますので、詳しくはYouTubeで探してみてください。
地域ごとの作り方やコツを、動画でわかりやすく説明してくれている方がたくさんいます。
忙しい中でも、たった一度きりの「最後のご飯」。
ぜひ、心をこめて作ってみてください。

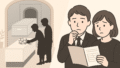

コメント