仏教形式のお葬式ではおなじみの「位牌」。
白木の位牌に戒名が書かれ、四十九日法要のあとには黒塗りの本位牌へ…という流れが一般的です。
でも、無宗教葬や直葬では話が変わってきます。
そもそも宗教者を呼ばず、読経もない。
戒名も当然なく、「宗教にとらわれないお見送り」が基本です。
そのため、“位牌を用意する必要はない”──のですが……。
なんとなく「拝む対象」が欲しい日本人の気質?
不思議なことに、無宗教葬でも「位牌っぽいものを用意したい」と希望されるご家族が、けっこういらっしゃいます。
「仏式じゃないけど、なにか手を合わせる対象がないと落ち着かなくて…」
「写真とお花だけじゃ、さびしい気がして…」
こういった感覚は、日本人特有の“拝む文化”によるものかもしれません。
なので最近では、戒名の代わりに生前のお名前(俗名)で作った本位牌のご依頼も、仏壇屋さんでは増えているそうです。
いわゆる「俗名位牌」ですね。
でも、その後どうするの?
お葬式の時は良かったとして──
問題はその後です。
たとえば四十九日。そもそも無宗教葬においては「四十九日法要」という概念自体がありません。
それなのに、「親戚が来るから…」となんとなく形式的に行ったり、納骨の節目でまた祭壇を用意したりするご家族もいます。
すると、こんな質問が多くなるのです。
「この位牌、もう使わないんですけど…どうしたら?」
結論から言うと、葬儀社でお引き取りすることもできます。
ただ、本来“不要だった”ものでもあるので、ご家族の判断次第。
手元供養として残す方もいれば、処分を希望される方もいます。
白木位牌? 黒塗り位牌? 名前だけでも意味がある?
ちなみに、仏式では葬儀当日に使うのが白木の位牌、
四十九日で仏壇用の黒塗り本位牌に「魂移し」をする流れです。
でも無宗教葬ではそういった区別もなく、
最初から黒塗り位牌を俗名で作るケースも珍しくありません。
形式は違えど、「この名前を書いて残すこと」にご家族の想いがこもっているのかもしれませんね。
まとめ:無宗教葬でも“手を合わせる場所”がほしい
宗教がなくても、心の拠り所は必要。
形式にとらわれないお葬式だからこそ、
逆に“何を残すか”をじっくり考える機会にもなります。
位牌が必要かどうか──
正解はありません。
でも、「俗名の位牌」をあえて作る方がいるのは、
やっぱり日本人らしい“祈りのカタチ”なのかもしれません。


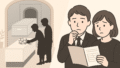
コメント