「開式前にお焼香」はNG?実はちょっと恥ずかしい失敗です
お通夜に参列する際、受付を済ませたあと式場に入ると、まずご遺影とご遺体が安置された祭壇が目に入ります。
「先にお参りをしておこう」と思うのはごく自然なことですが、そこで“お焼香”をしてしまう人、実はけっこういます。
でも、それ、実はちょっと間違いなんです。
お通夜の開式前に行うのは、「線香をあげる」こと。
“お焼香”は、僧侶の読経が始まった後、つまり式中に行うのが正式な流れです。
焼香台が用意されていても、それはあくまで式中用。
開式前は、祭壇の前に小さな香炉があり、線香が置かれているのが一般的です。
なぜ間違える?「お焼香」と「線香」の混同
そもそも「お焼香」と「線香」、どちらも“香を供える”行為なので混同されがちですが、
仏式の儀式ではしっかり役割が分かれています。
- 線香…開式前のお参り(自由参拝)に使う
- お焼香…式中に僧侶の読経に合わせて行う正式なお参り
葬儀スタッフ側としては「知らないのは仕方ないな」と思いますが、
堂々と間違ってしまうと**目立つうえに、意外と“恥ずかしい”**ものです。
「お顔見たい」と思うなら、到着時間に注意
「故人のお顔を見ておきたい」「しっかり手を合わせたい」――
そう思う気持ちは皆同じですが、ぎりぎり到着では難しいケースもあります。
というのも、式の10分前には“前机(まえづくえ)”の準備が始まるからです。
※前机とは、僧侶が読経で使う道具一式を置く祭壇前のテーブルのこと。
この机が置かれると、祭壇の前に立つことも、故人のお顔を見ることもできなくなります。
つまり、開式ギリギリでは線香をあげるタイミングすら失う可能性もあるということ。
理想の到着時間:最低15分前、できれば20分前
受付の混雑や、会場内での案内なども含めると、
「15〜20分前」には葬儀場に到着しておくのが安心です。
早く入りすぎても場にそぐわないと思われがちですが、
葬儀の場では“早め行動”が何よりのマナー。
意外な落とし穴「葬儀場って、時計がない?」
これも豆知識のひとつですが、
なぜか葬儀場には「壁掛け時計」が設置されていないことが多いのです。
理由は明確にはされていませんが、
「時を気にせず故人と向き合う空間を大切に」という配慮かもしれません。
そのため、自分のスマートフォンや腕時計でこまめに時間をチェックすることが大切です。
(スタッフに「あと何分ですか?」と聞いてもOK)
関連リンク:「通夜の参列、何時に行けばいいの?」はこちらの記事もチェック!
まとめ:開式前のお参り、正しい流れはこう!
- 受付を済ませる(できれば20分前に到着)
- 式場内へ案内されたら、祭壇前に進む
- 線香があれば、静かに一礼して手向ける
- 故人のお顔が見られる時間があれば、そっとお別れを
- 焼香は、僧侶の読経が始まった後に順番で行う
小さなマナーの積み重ねが、葬儀という場においてはとても大切。
事前に知っておくだけで、「あの人、よく知ってるな」と一目置かれるかもしれませんよ。


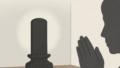
コメント